フランスワインの歴史
アルザス の 歴史

この地の葡萄栽培は、ローマ時代に始まったことは確かだが、6世紀末の民族の大移動が終わり、定住確立後、広大な司教区と修道院の領地の創設がその発展の基である。
中世の主要交易路であるライン河に近接しているアルザスは、ライン河を通じ、下流域各地や更にハンザ同盟諸都市とワイン交易を活発に行い、
スカンジナビア半島やイギリスまで、そのワインを輸出していた。
その絶頂期は16世紀だが、17世紀に入って起きた30年戦争(1616~48年)によって、アルザスの葡萄栽培とワイン交易を徹底的に荒廃した。
しかし、国際都市ならではのズトラスブルグの復活が原動力になって、18世紀中葉には、アルザスの葡萄栽培は奇跡的に復興する。
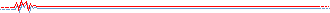
フランス革命後のアルザス
フランス革命は、アルザスには悪影響を与えた。広大な教会の領地の解体と共に、ライン河を利用した伝統的販路が閉ざされ、そらが並酒の生産に向わせ、輸出は半分に急落。 加えて、南フランスのワインとの競合の時代に突入して行くのである。 1871年、ドイツ帝国に併合されたアルザスのワインは第一次大戦終了まで、地方での消費とドイツワインの改良に充てられた。 1918年フランスに復帰したアルザスは、その後のナチス支配など再三に渡る困難な時代を凌ぎ、優良品種の再植と、平地から丘陵への転地を行い、高品質のワインを造り、ライン沿岸、ベネルックス、イギリス、デンマークに、中世以来の市場を持つことになるのである。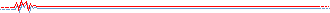
帰属をめぐるフランスとドイツの争い
アルザスは、その帰属をめぐるフランスとドイツの激しい争いの歴史に揉まれ、幾度かフランスとドイツの間を往復してきた。 その波瀾に富んだ歴史の推移が葡萄栽培にも大きく影響している。 葡萄畑が大勢の所有者に細分化されているのは、紛争が頻繁だったことによる。13,000haの畑に8,000人前後の所有者と言う極端な細分化(平均10アール前後)の現状は、耕地の整理統合や再編成を不可能にしている。 しかし、アルザスの人々は、この歴史的激動を、共同組合の機能強化に繋げ、現在は、これにネゴシアンと個人経営者を加え、製品の商品化に関し平等のパートを分担すると言う体制を固め、アルザスワインの更なる発展に努めている。
目 次・・・詳細
修道院の財政と葡萄栽培

6世紀後半には、ストラスブール司教区がアルザスのキリスト教の布教センターの役割を果たし、6~8世紀には、次々と各地に教区と修道院が建てられた。
信仰面だけでなく、知的センターの役割も担っていたのが修道院だったから、領主から葡萄園や田畑・森の寄進を受け富裕化して行った。
大土地所有者となった修道院は、多数の農奴的小作人を抱えながら、葡萄園の開発と経営を積極的に進めた。それが今日の葡萄園の基礎を築くことになる。
800年頃からの100年間で、アルザスのブドウを栽培する村は、120から170までに増え、その殆どが修道院の管轄下にあった。
修道院が葡萄園経営に関心を抱いた要因
ワインは、キリスト教の祭祀や領主への饗応・巡礼者への世話などに必要とされていたこともあるが、良質のワインは高い商品価値を持ち、その対価は何よりも確かな修道院の財政基盤の基だったことも重要な要素である。そのワインがもたらす莫大な富の姿は、修道院の記録にはっきりと記されている。 中世末の記録だが、アンロー女子大修道院の1505年の自家消費のワインは、384ヘクトリットル(ボトル換算で、51,200本)。当時この修道院に起居する尼僧数は2~30人で、この数字には、慈善や高位の来訪者の饗応はもとより、修道院で働く者(執事・代訴人[修道院の権利保護・裁判事務を担う]・収税人〔小作料等〕・職人〔大工、画師、彫師、家具師〕・森番等)への報酬が含まれている。 豊作の1520年のワインの総生産量は、1668ヘクトリットル(現在のボトル換算で、222,400本)で、自家消費を除いたものは総て商人を通して売り払っている。つまり、222,400本の約4分の3のワインが換金され修道院の財政を潤している。
修道院が良質のワインを産み出し得た要因
中世初期では、ローマ・カソリック教会の持つネットワークが、唯一の確かな情報ネットワークであった。このネットワークから、最上級のブドウ株の導入・移植・品種改良の情報がもたらされた。その情報を基に、その土地にあった品種改良と栽培技術の切磋琢磨が行われた。修道院には肉体的労役を厭わない教義と高い知的レベルがあったからである。中世アルザスのワイン商人の活躍と都市の発展
世俗の権力者である領主は、司教や修道院には、格別の庇護や免税などの特権を与えていた。この特権によって、司教や修道院は一般住民よりはるかに優遇された条件下で、葡萄を栽培しワインを造っていた。そして、そのワインの販売は商人を使って行っていた。
9世紀後半以降、このワイン商人は、教会の持つ通商や免税などの特権の下に、隣接するスイス方面は言うに及ばず、ライン下流域からスカンジナビアなど北海の彼方まで広範囲で活発な商取引を行い交易を拡大させた。
このワイン商人による交易拡大は、司教や修道院に莫大な利益をもたらし、司教権を増大させる基でもあるが、同時に、商人自身にも富をもたらし富裕化していくことになる。 アルザスの商人達は、ワインのみならず、麦、塩、茜(染料)を持ち出し、高級羅紗、皮革、羊毛、塩漬け鰊、干鱈等を持ち帰り、富を蓄積して行った。 それには、船頭・馬喰や職人など様々な職業の人の活動の支えと言う相関関係があってのことで、ストラスブールのような交通・交易の要所の街はそのような人々が集まり繁栄拡大していく。
今も残るストラスブールの旧市街と天高く聳える壮大なノートルダム大聖堂にその栄華の姿を見ることが出来る。 12~13世紀に、都市には「同業組合(コルボラシオン)」が組織される。ワイン商・毛皮商などの商人から船頭・パン屋・織物師・仕立屋・鍛冶屋などの職人にいたるまで、各種の同業組合が成立する。同業組合は、独自の規約をつくり、同一機能の排他的な利益保護や調停を図り力を蓄える。(1349年には、ストラスブール一市で28団体もあった) こうした都市の興隆には、封建領主が、都市市民にも通商の自由や特権を与えて、領内の経済の活性化を図ったことにあった。その裏に、ワインの販売による莫大な利益の下に、強大化する一方だった司教権に歯止めを掛けようとする、もうひとつの意図もあった。
9世紀後半以降、このワイン商人は、教会の持つ通商や免税などの特権の下に、隣接するスイス方面は言うに及ばず、ライン下流域からスカンジナビアなど北海の彼方まで広範囲で活発な商取引を行い交易を拡大させた。
このワイン商人による交易拡大は、司教や修道院に莫大な利益をもたらし、司教権を増大させる基でもあるが、同時に、商人自身にも富をもたらし富裕化していくことになる。 アルザスの商人達は、ワインのみならず、麦、塩、茜(染料)を持ち出し、高級羅紗、皮革、羊毛、塩漬け鰊、干鱈等を持ち帰り、富を蓄積して行った。 それには、船頭・馬喰や職人など様々な職業の人の活動の支えと言う相関関係があってのことで、ストラスブールのような交通・交易の要所の街はそのような人々が集まり繁栄拡大していく。
今も残るストラスブールの旧市街と天高く聳える壮大なノートルダム大聖堂にその栄華の姿を見ることが出来る。 12~13世紀に、都市には「同業組合(コルボラシオン)」が組織される。ワイン商・毛皮商などの商人から船頭・パン屋・織物師・仕立屋・鍛冶屋などの職人にいたるまで、各種の同業組合が成立する。同業組合は、独自の規約をつくり、同一機能の排他的な利益保護や調停を図り力を蓄える。(1349年には、ストラスブール一市で28団体もあった) こうした都市の興隆には、封建領主が、都市市民にも通商の自由や特権を与えて、領内の経済の活性化を図ったことにあった。その裏に、ワインの販売による莫大な利益の下に、強大化する一方だった司教権に歯止めを掛けようとする、もうひとつの意図もあった。
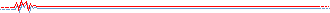
グールメ
ワイン交易が活発で需要が増大すると、悪徳商人が暗躍するのは世の習いで、当時、アルザスでも混ぜ物や変造が横行する。
この悪弊に対して、ブドウ栽培者・醸造者・商人の同業組合が行政当局と共同で様々な規制を設け、ワインの取引と品質管理を行うのだが、何といっても、グールメの誕生が大きな働きをなした。
グールメは、ワインの生産者と顧客の間で、利き酒、値付けはもとより、売買斡旋から出荷までの一連の業務を通して力を振るった。グールメは同業者組合から選らばれた地域の名士が担ったから、時には権力の乱用もあったが、おおむね鑑定には信が置かれ、ワイン取引に貢献した。このワイン鑑定人が、後世、料理鑑定人へと変貌していく。
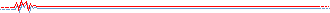
同 業 組 合
14世紀にアムメルシュウィールで結成された富裕市民たちの Herrenstubengesellschaftから出発した組織で,市吏や司祭,裁判官たちなどを主たるメンバーとする。Stubenmeisterと呼ばれる団長を中心とし,ほとんど毎日のように本部に集まっては飲食や談笑やゲームに興じていた。入会資格はメンバーの推薦とするが,ワインのきき酒試験に合格しなければならなかった。そして,合格者は1年間見習い団員としてワインの鑑定力を磨き,再びより高度なきき洒試験に合格して,初めて親方団員となることができた。 こうした入団システムは明らかに一般の職人組合のそれを踏襲したもので,たとえば物故メンバーの息子は無条件で入団が認められていた。また、集会では政治的・宗教的な議論が禁じられ、しかるべき恰好をせずに集会 に臨んだり、相手構わずワインを飲ませたり、正当な理由もなしに集会に欠席したりした者に対しては、罰金としてワイン3本の供出が課された。 このサン・テチエンヌ同宗団は今日もなお存在し、アルザス・ワインの普及のための様々な活動を活発に展開している。 試飲会、品質評価会、優秀ワインの保管、団員の就任式等の公式行事だけでなく、キエンツェムにおける一種の社交界をも形成している。


30年戦争(1618~1648)とアルザスワイン

絶頂期にあったアルザスワインは、17世紀に入って起こる、「30年戦争」(1616~48年)に、アルザス全土が巻き込まれたことによって、衰退する。
「30年戦争」は、ドイツのプロテスタントとカトリックの敵対から始まったが、最後は、この宗教に関係なく、西欧列強国の覇権争いの形をなし、西欧の殆どの国を巻き込んだ、ヨーロッパの最も破滅的な戦争である。主戦場であったドイツを始めとする北欧の破壊は著しく、西欧の歴史を100年以上逆戻りさせたと言われ、列強国の勢力地図の塗り変え以外、歴史的成果の全く見出せない戦争である。
アルザスは、その経済をフランスより、ライン河流域に依存していたから、この戦争による影響をまともに受けた。 アルザスの経済を大きく後退させたのは、 この戦争によって、最大の市場であるライン河流域から北方に至る販路が荒廃したこと。
飢饉やペストも手伝って、アルザスの農民たちの多くは、焦土化した村を捨てて大都市へ逃れ、ブドウ栽培地の村の多くが、廃村に追い込まれたこと。
加えて、交易の中心地ストラスブールは国際都市であったため、各国の様々な通貨が流通していたのだが、 その通貨統一を計るべく、30年戦争後、アルザスを支配下に治めたフランス王制の新通貨が劣悪だったため、通貨システムは全く功を奏さず、物価の上昇、領主の財政のいきずまりによる増税を引き起こし、住民の困窮と流通市場の混迷に拍車が掛かったこと等があげられる。
アルザスは、その経済をフランスより、ライン河流域に依存していたから、この戦争による影響をまともに受けた。 アルザスの経済を大きく後退させたのは、 この戦争によって、最大の市場であるライン河流域から北方に至る販路が荒廃したこと。
飢饉やペストも手伝って、アルザスの農民たちの多くは、焦土化した村を捨てて大都市へ逃れ、ブドウ栽培地の村の多くが、廃村に追い込まれたこと。
加えて、交易の中心地ストラスブールは国際都市であったため、各国の様々な通貨が流通していたのだが、 その通貨統一を計るべく、30年戦争後、アルザスを支配下に治めたフランス王制の新通貨が劣悪だったため、通貨システムは全く功を奏さず、物価の上昇、領主の財政のいきずまりによる増税を引き起こし、住民の困窮と流通市場の混迷に拍車が掛かったこと等があげられる。
奇跡的に蘇るアルザスワイン
混迷した経済と戦禍によって荒廃した葡萄栽培は、18世紀中葉から後期に掛けて奇跡的に復興する。それは、都市人口の増加が新しい市場を作ったからである。 30年戦争後、荒廃した自国を逃れ、移住して来たドイツ人やスイス人を始めとする周辺の国々の人々とその子孫に加え、近代工業化の波が、都市に人を集めた。 無論、ペスト禍や戦禍が遠のき、平和が訪れたことが最大の要因であるが、様々な人種や文化が交錯し、時代の流れを吸収して留まることのない国際都市ストラスブルグという町が復興の牽引車であったことは間違いない。
アルザスゆかりの文化人-1
アルザスのストラスブールは、ヨーロッパの中央にあって、自由な市民活動、経済的繁栄、中世以来の文化の蓄積、宗教問題への寛容性を持つ国際都市で、多彩な文化人を生み育ている。
(Johannes Gutenberg 1400?~1468) ストラスプールの大聖堂の前を出た通りに、その功績を記念したグーテンベルク広場がある。 彼が、ストラスプールで印刷機械を発明したということに一般的にはなっているが、印刷術の発展に関する話はもう少し複雑で、誰が印刷術の発明者かについての論争は続いている。 しかし、印刷のような技術は、ある日突然、誰かによって発明されたと言う事はまず考えられないから、発明者を争うのはあまり意味がない。
欧州の色々なところので、印刷に関する発見や改良がなされ、それが相互に重なり、活字印刷技術が発展していく流れの中で、グーテンベルグが最も重要な働きをしたことは間違いない。 マインツ生まれのクーテンベルグが、ストラスブルグにやって来たのは1434年で、初めは、金細工師としての仕事をしていたらしい。 印刷に関しては、最初、3人の有志と企業化を試みたが失敗に終わった。50年ごろマインツにもどり、同じ金細工師のヨハン・フストと提携して印刷機を製作し、比較的小型の書籍や一枚刷りの刷り物の印刷を始めた。 「グーテンベルク聖書」あるいは「四十二行聖書」などの名で有名なラテン語の大判聖書も、おそらくはこの印刷機で印刷されたようだ。
55年、フストに資金返済の訴訟を起され、印刷所を失う。 フストと決裂の後も、グーテンベルグはマインツとその近郊のエルトビルで印刷業を続け、その業績が認められ、65年にマインツ大司教アドルフ2世の庇護を受けることになる。 クーテンゲルグ 印刷術は、1460年代にアルプスを越えイタリアへ、ついでパリ、ロンドンに入った。宗教書から、科学書、ギリシャ・ローマの古典が印刷の対象になり、16世紀のルネッサンスの起動力になった。
グーテンベルグ
(Johannes Gutenberg 1400?~1468) ストラスプールの大聖堂の前を出た通りに、その功績を記念したグーテンベルク広場がある。 彼が、ストラスプールで印刷機械を発明したということに一般的にはなっているが、印刷術の発展に関する話はもう少し複雑で、誰が印刷術の発明者かについての論争は続いている。 しかし、印刷のような技術は、ある日突然、誰かによって発明されたと言う事はまず考えられないから、発明者を争うのはあまり意味がない。
欧州の色々なところので、印刷に関する発見や改良がなされ、それが相互に重なり、活字印刷技術が発展していく流れの中で、グーテンベルグが最も重要な働きをしたことは間違いない。 マインツ生まれのクーテンベルグが、ストラスブルグにやって来たのは1434年で、初めは、金細工師としての仕事をしていたらしい。 印刷に関しては、最初、3人の有志と企業化を試みたが失敗に終わった。50年ごろマインツにもどり、同じ金細工師のヨハン・フストと提携して印刷機を製作し、比較的小型の書籍や一枚刷りの刷り物の印刷を始めた。 「グーテンベルク聖書」あるいは「四十二行聖書」などの名で有名なラテン語の大判聖書も、おそらくはこの印刷機で印刷されたようだ。
55年、フストに資金返済の訴訟を起され、印刷所を失う。 フストと決裂の後も、グーテンベルグはマインツとその近郊のエルトビルで印刷業を続け、その業績が認められ、65年にマインツ大司教アドルフ2世の庇護を受けることになる。 クーテンゲルグ 印刷術は、1460年代にアルプスを越えイタリアへ、ついでパリ、ロンドンに入った。宗教書から、科学書、ギリシャ・ローマの古典が印刷の対象になり、16世紀のルネッサンスの起動力になった。

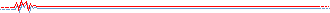
アルバート・シュヴァイツアー
(Albert Schweitzer 1875~1965)
シュヴァイツアーはアルザスが生んだノーベル平和賞受賞者である。ストラスブール大学、パリ大学、ベルリン大学などで哲学、神学、医学を学んだ後、1900年、ストラスブールの聖ニコラス教会の聖職者となり、翌年、宗教哲学の講師となる。
オルガン奏者としても名声を得ており、特に、バッハの音楽における宗教的な特性を強調し、単調で直線的な演奏形式を唱え、後の標準的な演奏スタイルを確立した。
その音楽的基盤はフランスかドイツかと問うが、この二つが結びついたアルザス文化の良い見本が、シュヴァイツアー芸術であると言えるであろう。 国と国との垣根を越えた普遍性をシユヴァイツアーその人の人格が持っている。赤道アフリカのランバレネ(現ガボン共和国)に於ける、ハンセン病患者を含む多くの病人への、彼の献身的医療活動を知っている人は少なくないが、その医療活動を支えたのは、彼自身の音楽演奏のレコードからの収入であったことを知る人は少ない。
ある時は哲学・神学者、ある時は医者、音楽家として多彩な活動をしながら、一人の人間としてシュヴァイツアーが体現していったのは、「人類の平和の道」であった。 最晩年は核兵器廃絶に献身的な努力を重ねた。この人ほどノーベル平和賞受賞者としてふさわしい人はいない。
その音楽的基盤はフランスかドイツかと問うが、この二つが結びついたアルザス文化の良い見本が、シュヴァイツアー芸術であると言えるであろう。 国と国との垣根を越えた普遍性をシユヴァイツアーその人の人格が持っている。赤道アフリカのランバレネ(現ガボン共和国)に於ける、ハンセン病患者を含む多くの病人への、彼の献身的医療活動を知っている人は少なくないが、その医療活動を支えたのは、彼自身の音楽演奏のレコードからの収入であったことを知る人は少ない。
ある時は哲学・神学者、ある時は医者、音楽家として多彩な活動をしながら、一人の人間としてシュヴァイツアーが体現していったのは、「人類の平和の道」であった。 最晩年は核兵器廃絶に献身的な努力を重ねた。この人ほどノーベル平和賞受賞者としてふさわしい人はいない。

アルザスゆかりの文化人-2
ゲーテ
(Johann Wolfgang Von Goethe 1749~1832)
ゲーテは、ライプチヒ大学で法律学を学んだ後、青春真っ只中の20歳の頃、ストラスブールにやって来て、哲学、文学、医学の講義を受け、1771年8月、ストラスブール大学の学位を無事取得している。
ゲーテは、ストラスブールで、彼の文学的生涯にとって重要な、2人の人物に出会っている。1人は、近郊のゼーゼンハイムの牧師の娘フリーデリケ・ブリオンで、彼女は後に、「ファウスト」のグレートヒェンなど、いくつかの作品のモデルとなっているが、「詩と真実」には彼女への愛がアルザスの田園と一体化したような形で語られている。
もう1人は、彼の青春時代にもっとも大きな知的刺激を与えたとされる、哲学者で批評家のヘルダーであった。ヘルダーは、当時のドイツに広く流行していたフランス古典主義の理論を捨て、感情を直接表現するシェークスピアの演劇を評価することを、ゲーテに教えた。 また、ドイツ文学の発展のためのすぐれた源泉として、ドイツの伝承詩歌とゴシック美術を再認識することを促がした。 「シュトュルム・ウント・ドランク(疾風怒涛)」の運動に対する18世紀のフランス社会思想の影響の強さはよく指摘される事であるが、ゲーテのストラスブール留学の成果が後になって芽を出したものである事は間違いない。
もう1人は、彼の青春時代にもっとも大きな知的刺激を与えたとされる、哲学者で批評家のヘルダーであった。ヘルダーは、当時のドイツに広く流行していたフランス古典主義の理論を捨て、感情を直接表現するシェークスピアの演劇を評価することを、ゲーテに教えた。 また、ドイツ文学の発展のためのすぐれた源泉として、ドイツの伝承詩歌とゴシック美術を再認識することを促がした。 「シュトュルム・ウント・ドランク(疾風怒涛)」の運動に対する18世紀のフランス社会思想の影響の強さはよく指摘される事であるが、ゲーテのストラスブール留学の成果が後になって芽を出したものである事は間違いない。

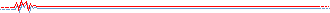
パスツール
(Louis Pasteur 1822~1895年) ストラスプール大学は、1968年の学制改革によって、3つの大学に分かれている。第一大学は、医学部と経済学部を柱として物理学、生物化学など自然科学系領域を擁する大所帯で、通常、ルイ・パスツール大学と言う。第一大学がルイ・パスツールの名を冠したのは、彼が1849~1854年までストラスプール大学の教授を勤めていたからである。 ストラスブールで数年を研究についやしたのち、1854年にリール大学に移り、化学教授、理学部長となった。この学部の設立の理念に、化学を同地方の産業、とくにワインやビールを醸造するうえでの問題に応用することがあった。
彼はただちに、発酵過程の研究に没頭した。酵母が発酵になんらかの役割をはたしていると考えたのは、彼が最初ではなかった。
しかし、以前行った化学的特異性の研究を基に、ワインの腐敗(酸っぱくなる)は、望ましくない乳酸や酢酸など生じるからで、それは、細菌など余分な微生物が存在するためだということを示した。フランスでは、ワインやビールがすっぱくなる現象(酸敗)が、経済問題となっていた。 パスツールは、始めに、糖液を高温処理すれば細菌を除くことができることを示して、この問題を解決した。 現在のワイン醸造は、パスツールのこの研修成果の上に成り立っていると言っても過言ではない。 病気の細菌説を証明し、低温殺菌法を発明し、数々の病気のワクチンを開発し、近代微生物学の基礎を築きいた、この偉大な化学者の死に対しては、フランスは、国葬をもって、その栄誉と業績を讃えた。1895年のことである。

アルザス語
蔵持不二也氏の著書「ワインの民族誌」は、アルザスのワインと歴史・文化について興味を持たれる方に、是非お薦めの一冊である。ご紹介を兼ねて、アルザス語について書かれた一節を引用させて頂きます。
 (私、A氏に生命保険を奨めたいのですが、これならどんな事故でも保障します。ええ、重病の方でももちろん。少し割増しの保険料さえ払っていただけるのでしたら、契約を結びます)
アルザスに足を踏み入れると、たとえばこんな会話が聞こえてくる。初めてこの地を訪れた者にとつては、一瞬ドイツ語圏に迷い込んだような気がするが、よく聴くとそうでもない。なかにはフランス語(イタリック部)も混じっている。そこでようやく合点がいく。これがアルザス語というものなのだと。
ゴール人、アラマンやフランクなどのゲルマン人、ローマ人、ユダヤ人、さらにフランス人……と、
古来よりこの地に定住した民族は数多い。そんな彼らの持ち込んだ言語が、先住言語と競合しつつ、根付き、今日のアルザス語を形作っていったのである。
(私、A氏に生命保険を奨めたいのですが、これならどんな事故でも保障します。ええ、重病の方でももちろん。少し割増しの保険料さえ払っていただけるのでしたら、契約を結びます)
アルザスに足を踏み入れると、たとえばこんな会話が聞こえてくる。初めてこの地を訪れた者にとつては、一瞬ドイツ語圏に迷い込んだような気がするが、よく聴くとそうでもない。なかにはフランス語(イタリック部)も混じっている。そこでようやく合点がいく。これがアルザス語というものなのだと。
ゴール人、アラマンやフランクなどのゲルマン人、ローマ人、ユダヤ人、さらにフランス人……と、
古来よりこの地に定住した民族は数多い。そんな彼らの持ち込んだ言語が、先住言語と競合しつつ、根付き、今日のアルザス語を形作っていったのである。
従って、ひと口にアルザス語と言っても、そこにはさまざまな言語的系統が含まれる。
モーゼル県へと瘤状(ボシュ)につき出た最北西部のいわゆる「アルザス・ボシユ」地方では中部ドイツ語が、中央部では上部ドイツ語、最南部のスンゴー地方では高地アレマン語がそれぞれにアルザス語の母胎となっており、これにロマンス諸語のフランス語とドイツ系ユダヤ人たちの言語イディッシュが複雑に終み合っているのだ。 アルザスとはヨーロッパの中心部にありながら、いや、むしろその地理的条件ゆえに、民族の坩堝であり、アルザス語は言語の坩堝となっているのである。
面積約8300平方キロメートル。我が国の僅か2.2パーセント足らずのこの地ほど、多様な言語文化を宿命として背負っている地域はほかにほとんど例をみまい。そして今日、人々はドイツ人にはドイツ語、フランス人にはフランス語をこともなげに使い分けてみせる。むろん家族や仲間同士では、アルザス語主体の会話となる。
 (私、A氏に生命保険を奨めたいのですが、これならどんな事故でも保障します。ええ、重病の方でももちろん。少し割増しの保険料さえ払っていただけるのでしたら、契約を結びます)
アルザスに足を踏み入れると、たとえばこんな会話が聞こえてくる。初めてこの地を訪れた者にとつては、一瞬ドイツ語圏に迷い込んだような気がするが、よく聴くとそうでもない。なかにはフランス語(イタリック部)も混じっている。そこでようやく合点がいく。これがアルザス語というものなのだと。
ゴール人、アラマンやフランクなどのゲルマン人、ローマ人、ユダヤ人、さらにフランス人……と、
古来よりこの地に定住した民族は数多い。そんな彼らの持ち込んだ言語が、先住言語と競合しつつ、根付き、今日のアルザス語を形作っていったのである。
(私、A氏に生命保険を奨めたいのですが、これならどんな事故でも保障します。ええ、重病の方でももちろん。少し割増しの保険料さえ払っていただけるのでしたら、契約を結びます)
アルザスに足を踏み入れると、たとえばこんな会話が聞こえてくる。初めてこの地を訪れた者にとつては、一瞬ドイツ語圏に迷い込んだような気がするが、よく聴くとそうでもない。なかにはフランス語(イタリック部)も混じっている。そこでようやく合点がいく。これがアルザス語というものなのだと。
ゴール人、アラマンやフランクなどのゲルマン人、ローマ人、ユダヤ人、さらにフランス人……と、
古来よりこの地に定住した民族は数多い。そんな彼らの持ち込んだ言語が、先住言語と競合しつつ、根付き、今日のアルザス語を形作っていったのである。従って、ひと口にアルザス語と言っても、そこにはさまざまな言語的系統が含まれる。
モーゼル県へと瘤状(ボシュ)につき出た最北西部のいわゆる「アルザス・ボシユ」地方では中部ドイツ語が、中央部では上部ドイツ語、最南部のスンゴー地方では高地アレマン語がそれぞれにアルザス語の母胎となっており、これにロマンス諸語のフランス語とドイツ系ユダヤ人たちの言語イディッシュが複雑に終み合っているのだ。 アルザスとはヨーロッパの中心部にありながら、いや、むしろその地理的条件ゆえに、民族の坩堝であり、アルザス語は言語の坩堝となっているのである。
面積約8300平方キロメートル。我が国の僅か2.2パーセント足らずのこの地ほど、多様な言語文化を宿命として背負っている地域はほかにほとんど例をみまい。そして今日、人々はドイツ人にはドイツ語、フランス人にはフランス語をこともなげに使い分けてみせる。むろん家族や仲間同士では、アルザス語主体の会話となる。

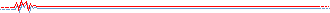
1982年の統計資料で言えば、ストラスプール鉄道管理局内の年間旅行者数はおよそ4000万に達するという。
グリューネヴァルトの祭壇画で有名なコルマールのウンテルリンデン美術館は、フランスでルーブル美術館に次ぐ入場者数を誇っているともいう。
これらアルザス訪問者のなかでは、フランス人(とドイツ人)の数が最も多いとされるが、はたして彼らが同国人の使うアルザス語をどこまで理解できるものか。事情は我が国の琉球語と酷似している。言語的隔絶。あえて言えばそうなるだろう。興味深いことに、この隔絶だけは社会的・文化的隔絶がほとんど解消されたと思われる今日でもなお歴然としている。 多少うがった見方をすれば、まさにそれが存在する限りにおいて、アルザス人たちはフランスにもドイツにも属さぬ自らのアイデンティティを強烈に保持できる。排除するものが、そうすることによって自らのアイデンティティを確立ないし維持するように、排除されるものもまたそうされることによって自らのアイデンティティと向き会う。 アルザスの歴史は過不足なくこうしたもう一つの排除の力学のうちにある(あった)。だとすれば、このアイデンティティこそが、アルザス人をしておそらく自らの負性の歴史を超克させるアンチ・テーゼとなるのではないか。・・・・「民族・言語の坩堝」
著者:蔵持不二也 1947年生まれ。早稲田大学文学部卒業後、フランス留学。
パリ第四大学修士課程、社会科学高等研究院前期樽士課程修了。 現在、早稲田大学人間科学部教授。
西洋史、人類学、民族学、考古学をつなぐ学際的研究と、ヨーロツパ民衆文化の古層を探るユニークな視点で注目されている。 主な著書に「祝祭の構図」(ありな書房) 「異貌の中世」(弘文堂)がある。
グリューネヴァルトの祭壇画で有名なコルマールのウンテルリンデン美術館は、フランスでルーブル美術館に次ぐ入場者数を誇っているともいう。
これらアルザス訪問者のなかでは、フランス人(とドイツ人)の数が最も多いとされるが、はたして彼らが同国人の使うアルザス語をどこまで理解できるものか。事情は我が国の琉球語と酷似している。言語的隔絶。あえて言えばそうなるだろう。興味深いことに、この隔絶だけは社会的・文化的隔絶がほとんど解消されたと思われる今日でもなお歴然としている。 多少うがった見方をすれば、まさにそれが存在する限りにおいて、アルザス人たちはフランスにもドイツにも属さぬ自らのアイデンティティを強烈に保持できる。排除するものが、そうすることによって自らのアイデンティティを確立ないし維持するように、排除されるものもまたそうされることによって自らのアイデンティティと向き会う。 アルザスの歴史は過不足なくこうしたもう一つの排除の力学のうちにある(あった)。だとすれば、このアイデンティティこそが、アルザス人をしておそらく自らの負性の歴史を超克させるアンチ・テーゼとなるのではないか。・・・・「民族・言語の坩堝」
「ワインの民族誌」 筑摩書房(ちくまライブラリー17)
著者:蔵持不二也 1947年生まれ。早稲田大学文学部卒業後、フランス留学。
パリ第四大学修士課程、社会科学高等研究院前期樽士課程修了。 現在、早稲田大学人間科学部教授。
西洋史、人類学、民族学、考古学をつなぐ学際的研究と、ヨーロツパ民衆文化の古層を探るユニークな視点で注目されている。 主な著書に「祝祭の構図」(ありな書房) 「異貌の中世」(弘文堂)がある。


