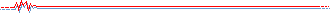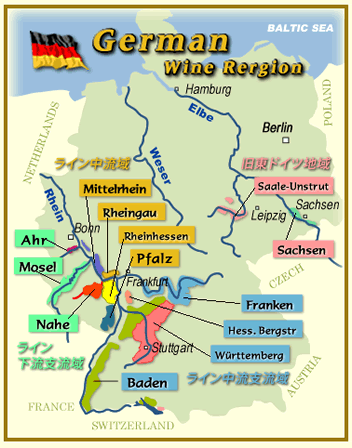ドイツワインの歴史ーTop
ドイツワインの歴史はラインの歴史とも言える
 ドイツの葡萄栽培は、古代ローマの時代に始まったことは確かだが、6世紀末の民族の大移動が終わり定住確立後、広大な司教区と修道院の領地の創設がその発展の基である。
古代からラインの水運はドイツ人の生活を支えてきた交易の大動脈である。
ドイツの葡萄栽培は、古代ローマの時代に始まったことは確かだが、6世紀末の民族の大移動が終わり定住確立後、広大な司教区と修道院の領地の創設がその発展の基である。
古代からラインの水運はドイツ人の生活を支えてきた交易の大動脈である。ライン河を通じ、下流域各地やハンザ同盟諸都市、更にはスカンジナビア半島やイギリスまで、ワイン交易を活発に行ってきた。
このライン交易に権力を振るい支配した司教の俗権の強大さもドイツの葡萄栽培に大きな影響を与えた。 葡萄栽培の北限にあることにもよるが、この交易の大動脈にあることも大きな要因であろう。 ドイツワインの歴史は、地理的に捉えればラインの歴史でもある。ここではその歴史をたどることにした。
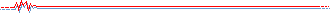
ドイツワインの歴史概要
| 1. | ドイツの葡萄栽培の始まり ドイツ最古のローマの都・トリーア(Trier)とモーゼル川流域の葡萄栽培。 |
|---|---|
| 2. | 中世初期キリスト教トフランケン ワインの守護聖人・キリアンとフランケン&フランク王国の実態。 |
| 3. | 神聖ローマ帝国 オットー1世の神聖ローマ帝国の性格&ウォルムスの協約。 |
| 4. | ラインの水運と大司教の強大な俗権 中世ヨーロッパ交易の大動脈・ラインと大司教の強大な俗権。 |
| 5. | 宗教改革と30年戦争 宗教改革と30年戦争のもたらしたドイツの荒廃。 |
| 6. | 疾風怒涛 ドイツ文化の開花。その文学と哲学。 |
| 7. | ヨハニスベルグ城とメッテルニッヒ ラインガウの名醸地・ヨハニスベルグ城とその城主・メッテルニッヒ。 |
| 8. | エーバーバッハ修道院とビスマルク ドイツワイン文化の華・エーバーバッハ修道院と熱血宰相・ビスマルク。 |
ドイツとフランスの対比
ドイツのワイン産地は、その殆どがライン河とその支流沿岸にある。
このドイツワイン産地の歴史と風土を知る上で、格好の本が、加藤雅彦著「ライン河」(岩波新書)である。
以下少々長いが、「対照的パートナー」と題し、ドイツとフランスを対比して語る部分を抜粋させて頂いた。
興味を持たれた方は、是非「ライン河」岩波新書にあたって頂きたい。
「ライン河-ヨーロッパ史の動脈-」 岩波新書
 著者:加藤雅彦
著者:加藤雅彦
1927年名古屋市生。東京大学法学部政治学科卒業後,NHK入局。 ベルリン自由大学留学,ベオグラード,ボン支局長,解説委員など歴任。現在一欧州問題研究家,ジャーナリスト。
著書:
『東ヨーロッパ』 日本放送出版
『ドイツとドイツ人』 日本放送出版
『中欧の崩壊一ウィーンとベルリン』 中央公論
『中欧の復活-ベルリンの壁のあとに』 日本放送出版
『ドナウ河紀行』日本エッセイストクラブ賞受賞 岩波
『バルカンーユーゴ悲劇の深層』 日本経済新聞社
『ハプスブルク帝国』 河出書房新社
『事典現代のドイツ』 共編著 大修館書店 訳書:
P.ミケル『ヨーロッパ最後の王たち』(監訳、創元社)ほか

1927年名古屋市生。東京大学法学部政治学科卒業後,NHK入局。 ベルリン自由大学留学,ベオグラード,ボン支局長,解説委員など歴任。現在一欧州問題研究家,ジャーナリスト。
著書:
『東ヨーロッパ』 日本放送出版
『ドイツとドイツ人』 日本放送出版
『中欧の崩壊一ウィーンとベルリン』 中央公論
『中欧の復活-ベルリンの壁のあとに』 日本放送出版
『ドナウ河紀行』日本エッセイストクラブ賞受賞 岩波
『バルカンーユーゴ悲劇の深層』 日本経済新聞社
『ハプスブルク帝国』 河出書房新社
『事典現代のドイツ』 共編著 大修館書店 訳書:
P.ミケル『ヨーロッパ最後の王たち』(監訳、創元社)ほか
岩波新書「ライン河」抜粋
国民と民族
ラインの西と東のパートナーはこうも違うものか。仏独両国をざつと比較しただけでも、その対照的な国情にいまさらながら驚く。まず最も基本的な国家と国民の形成についてみてみよう。
第一章でのべたように、両国ともその起源は、同じフランク王国にある。
843年の「ヴェルダン条約」で、シャルルマーニユ(カール大帝)の建設したこの広大な王国も分割され、独仏それぞれ別個の国としての歴史が始まったが、国家と国民の成り立ちはフランスとドイツとでは、まったくその過程を異にした。 フランスは「はじめに国家ありき」であった。そして国民は国家によって創られた。ドイツでは「はじめに民族ありき」であった。
国家が生まれたのはやっと19世紀になってからである。そしてその国家とともに国民も創られたのである。
フランスには、当初から均質な「民族」としてのフランス人なるものは存在しなかった。ケルト人(ガリア人)に、ローマ人、フランク族、ノルマン人(ヴァイキング)などが混血し、さらにバスク、ブルターニュ、アルザスなどのエスニック・グループがこれに加わって今日のフランス人が形成された。これらさまざまな種族からフランス「国民」(市民)を創り出したのが国家であった。 人種を超えた普遍的な「市民」の概念はフランス革命で確立されたが、それよりはるか以前、カペー朝のフィリップ美王(1268-1314)によって、事実上その先鞭がつけられていた。フィリップは、世界市民的なローマ法に精通したブレーンを従えていた。
以来フランスでは、人種の同化と融合は絶え間なく行われ、国家による「国民」の形成が進められたのである。以上はドイツとは根本的に異なる点である。 ドイツでは、フランスとは対照的に「民族」としてのドイツ人(ゲルマン)が当初から存在した。しかし彼らは、1871年のドイツ統一まで「国家」と「国民」を形成することができなかった。もっとも彼らは、中世にドイツ帝国(神聖ローマ帝国)を樹立した。しかしその帝国の実体は、今日いう国家とはおよそ似ても似つかぬものであり、1906年にナポレオンに解体され消滅したことはすでにのべた通りである。
この帝国の下では、プロイセン、オーストリアをはじめ、独立の大小ドイツ諸国が併存していたが、実際にはドイツという名の国家も国民も存在しなかつた。言語・文化を共にするドイツ人でありながら、彼らはそれぞれその帰属する国の国籍をもち、その国民として自らを意識していた。 「ドイツ国民」という意識は、ナポレオンのドイツ支配に反発するナショナリズムの中で、はじめて起こってきたものである。フランスは、メロヴィング朝か、「ヴェルダン条約」かあるいはカペー朝か、どこを起点とみるかによって多少異なるが、いずれをとっても国家の歴史は一千年を超える。
だがドイツの国家としての歴史は、たかだか130年にすぎない。ドイツ人がフランスを羨望してきたところである。 しかし一方でフランスは、均質的な単一民族としての歴史をもっていない。「はじめに民族ありき」のドイツ人を、フランスが恐れ警戒してきたゆえんである。この点では両国はまったく対極的といえよう。
843年の「ヴェルダン条約」で、シャルルマーニユ(カール大帝)の建設したこの広大な王国も分割され、独仏それぞれ別個の国としての歴史が始まったが、国家と国民の成り立ちはフランスとドイツとでは、まったくその過程を異にした。 フランスは「はじめに国家ありき」であった。そして国民は国家によって創られた。ドイツでは「はじめに民族ありき」であった。
国家が生まれたのはやっと19世紀になってからである。そしてその国家とともに国民も創られたのである。
フランスには、当初から均質な「民族」としてのフランス人なるものは存在しなかった。ケルト人(ガリア人)に、ローマ人、フランク族、ノルマン人(ヴァイキング)などが混血し、さらにバスク、ブルターニュ、アルザスなどのエスニック・グループがこれに加わって今日のフランス人が形成された。これらさまざまな種族からフランス「国民」(市民)を創り出したのが国家であった。 人種を超えた普遍的な「市民」の概念はフランス革命で確立されたが、それよりはるか以前、カペー朝のフィリップ美王(1268-1314)によって、事実上その先鞭がつけられていた。フィリップは、世界市民的なローマ法に精通したブレーンを従えていた。
以来フランスでは、人種の同化と融合は絶え間なく行われ、国家による「国民」の形成が進められたのである。以上はドイツとは根本的に異なる点である。 ドイツでは、フランスとは対照的に「民族」としてのドイツ人(ゲルマン)が当初から存在した。しかし彼らは、1871年のドイツ統一まで「国家」と「国民」を形成することができなかった。もっとも彼らは、中世にドイツ帝国(神聖ローマ帝国)を樹立した。しかしその帝国の実体は、今日いう国家とはおよそ似ても似つかぬものであり、1906年にナポレオンに解体され消滅したことはすでにのべた通りである。
この帝国の下では、プロイセン、オーストリアをはじめ、独立の大小ドイツ諸国が併存していたが、実際にはドイツという名の国家も国民も存在しなかつた。言語・文化を共にするドイツ人でありながら、彼らはそれぞれその帰属する国の国籍をもち、その国民として自らを意識していた。 「ドイツ国民」という意識は、ナポレオンのドイツ支配に反発するナショナリズムの中で、はじめて起こってきたものである。フランスは、メロヴィング朝か、「ヴェルダン条約」かあるいはカペー朝か、どこを起点とみるかによって多少異なるが、いずれをとっても国家の歴史は一千年を超える。
だがドイツの国家としての歴史は、たかだか130年にすぎない。ドイツ人がフランスを羨望してきたところである。 しかし一方でフランスは、均質的な単一民族としての歴史をもっていない。「はじめに民族ありき」のドイツ人を、フランスが恐れ警戒してきたゆえんである。この点では両国はまったく対極的といえよう。
中央集権と地方分権
両国の政治の仕組みをみても、その間にはきわだった対照がみられる。フランスの強大な大統領制とドイツの議院内閣制からして大きな違いがみられるが、より顕著なのは前者の中央集権制に対する後者の地方分権制である。
フランスはその発端から、ひたすら王権を強化し、王領を拡大することによって形成され発展した国家である。パリとオルレアン一帯を支配するにすぎなかったカペー朝初期の所領が、ほぼ今日のフランス本土全域にまで拡大されたのは、17世紀ルイ14世の時代であるが、これをもたらしたのは、歴代の王が一貫して行なった力による征服の結果に他ならなかった。その国土膨張の過程で、支配を維持し統一を強化するために確立されたのが、パリを中心とする中央集権制度であった。
フランスのこの強力な中央集権制こそ、外に対しては、イギリスとの百年戦争や、新旧両教の争いから起きた三十年戦争など、国家崩壊と分裂の危機を見事にのり越えさせ、内においては、さまざまな人種をフランス国民として同化することを可能ならしめたのである。
フランス革命で王政は打倒されたが、中央集権制度は生き残っただけでなく、革命とその後のナポレオン時代にさらに強化されて今日に至っている。フランスの「偉大さ」もこの中央集権制なしにはありえなかったであろう。
一方ドイツでは、1971年の統一以後も、歴史的な諸国並立の状態は引き継がれ、ヒトラー時代と戦後の東ドイツをのぞいて、今日まで地方分権制を維持してきた。鉄血宰相ビスマルクによって実現されたドイツ帝国も、決して一枚岩の統一国家ではなく、連邦制の下に樹立された国家であった。26の邦から構成され、そのうち22邦は従来通り君主制を維持し、それぞれ君主の統治下にあった。22邦とは、プロイセン、バイエルン、ザクセン、ヴュルテンベルクの4つの王国、それに6つの大公国、5つの公国、7つの侯国である。これらに、ハンブルクをはじめ3つの自由ハンザ都市、それに帝国直轄地としてエルザス・ロートリングン(アルザス・ロレーヌ)が加わって連邦を構成した。
第一次世界大戦での敗戦の結果、帝政が崩壊して共和制(ワイマル共和国)に移行するが、この共和制(1919-32)下においても、16の州からなる連邦制を維持した。 第二次大戦後西ドイツは、11の州を設けてヒトラー時代に中断された連邦制を復活した。1990年のドイツ再統一後は、東ドイツも5州に再編成されて西ドイツに吸収され、現在のドイツは16の州(そのうち3つは州と同格の市)からなる連邦制をとっている。
ドイツの地方分権は、第一に教育・文化にいちじるしい。ドイツには中央に文部省がなく、教育は州政府の管轄下にあり、各州それぞれ異なる教育行政が行われている。第二には財政である。たとえば中央と地方の予算配分をみると、ドイツでは連邦(中央)政府の取り分がわずか40%であるのに対し、フランスでは70%以上を国がにぎっている。第三は国政に対する地方のチェックである。ドイツの連邦参議院(上院)は、各州政府から任命された議員から構成されており、彼らは州政府の意志に拘束されている。第四にマスメディア、ことに放送である。国営放送中心のフランスに対し、ドイツでは、各州が共同で公共放送を運営している。しかもフランスでみられるような政治の介入を避けるため、州それぞれ各界多様な代表からなる放送審議会が運営に参加する。なお各州には、連邦の越権に対して、憲法裁判所への提訴の道が開かれている。 一方、対極にあるフランスも、ミッテランの社会党政権の下で、中央集権制の弊害を認めて1982年から地方分権に向けて動き始めた。しかし千年を通じてフランスを支えてきた国家の屋台骨に手をつけるようなものであるとか、「封建領主」を復活して国家を解体に導くにひとしいとか、財政破綻や汚職を招くだけだと、分権反対の声は根強い。しかも前途に立ちはだかる壁もまた、きわめて厚い。
まずこの国独特のエリート養成校、国立行政学院ENA出身者で固めた政官界指導層、それに中央と地方の公職兼務の慣行(たとえば大臣職と市長職)、さらには極度に細分化された行政単位(市町村の数はドイツの三倍)など、問題は山積しているのが現状である。
一方ドイツでは、1971年の統一以後も、歴史的な諸国並立の状態は引き継がれ、ヒトラー時代と戦後の東ドイツをのぞいて、今日まで地方分権制を維持してきた。鉄血宰相ビスマルクによって実現されたドイツ帝国も、決して一枚岩の統一国家ではなく、連邦制の下に樹立された国家であった。26の邦から構成され、そのうち22邦は従来通り君主制を維持し、それぞれ君主の統治下にあった。22邦とは、プロイセン、バイエルン、ザクセン、ヴュルテンベルクの4つの王国、それに6つの大公国、5つの公国、7つの侯国である。これらに、ハンブルクをはじめ3つの自由ハンザ都市、それに帝国直轄地としてエルザス・ロートリングン(アルザス・ロレーヌ)が加わって連邦を構成した。
第一次世界大戦での敗戦の結果、帝政が崩壊して共和制(ワイマル共和国)に移行するが、この共和制(1919-32)下においても、16の州からなる連邦制を維持した。 第二次大戦後西ドイツは、11の州を設けてヒトラー時代に中断された連邦制を復活した。1990年のドイツ再統一後は、東ドイツも5州に再編成されて西ドイツに吸収され、現在のドイツは16の州(そのうち3つは州と同格の市)からなる連邦制をとっている。
ドイツの地方分権は、第一に教育・文化にいちじるしい。ドイツには中央に文部省がなく、教育は州政府の管轄下にあり、各州それぞれ異なる教育行政が行われている。第二には財政である。たとえば中央と地方の予算配分をみると、ドイツでは連邦(中央)政府の取り分がわずか40%であるのに対し、フランスでは70%以上を国がにぎっている。第三は国政に対する地方のチェックである。ドイツの連邦参議院(上院)は、各州政府から任命された議員から構成されており、彼らは州政府の意志に拘束されている。第四にマスメディア、ことに放送である。国営放送中心のフランスに対し、ドイツでは、各州が共同で公共放送を運営している。しかもフランスでみられるような政治の介入を避けるため、州それぞれ各界多様な代表からなる放送審議会が運営に参加する。なお各州には、連邦の越権に対して、憲法裁判所への提訴の道が開かれている。 一方、対極にあるフランスも、ミッテランの社会党政権の下で、中央集権制の弊害を認めて1982年から地方分権に向けて動き始めた。しかし千年を通じてフランスを支えてきた国家の屋台骨に手をつけるようなものであるとか、「封建領主」を復活して国家を解体に導くにひとしいとか、財政破綻や汚職を招くだけだと、分権反対の声は根強い。しかも前途に立ちはだかる壁もまた、きわめて厚い。
まずこの国独特のエリート養成校、国立行政学院ENA出身者で固めた政官界指導層、それに中央と地方の公職兼務の慣行(たとえば大臣職と市長職)、さらには極度に細分化された行政単位(市町村の数はドイツの三倍)など、問題は山積しているのが現状である。
ハイテクと伝統的ものづくり
フランスがドイツに対して脅威を感じているのは、その経済力である。ドイツ経済はなぜ強いのか。これにも歴史的な背景が存在する。由来フランスは「うまし国」と呼ばれ、温和な自然に恵まれた実り豊かな土地である。農業で国は十分に養われてきた。
だが自然条件の厳しいドイツでは農業だけに依存するわけにはいかなかった。彼らは中世以来商業によって生きる術を身につけ、バルト海貿易を通じて繁栄したハンザ都市をはじめ、多くの都市が交易によって富を集めた。 一方フランスでは、当時商業は貴族の間では「恥ずべき行為」として排斥され、これに従事したものは貴族の特権を剥奪されていた。
宗教改革の時代に、ドイツでプロテスタントが優勢となり、フランスがカトリシズムを貫き通したことも、その後の両国経済の発展に少なからざる影響を残した。
フランスでは1695年、ルイ14世がナントの勅令を撤回して新教を禁止したが、このため20万の新教徒(ユグノー)がプロイセンやオランダに亡命した。これによって国家統一の基盤は強化されたものの、経済発展の活力が奪われたという点では実に大きなマイナスであった。
プロテスタントには、勤勉で技能を身につけ企業家精神に富む人材が多数いたのに対し、金銭を稼いで富を築くことを嫌うカトリシズムは、本質的には近代の資本主義精神にはなじまなかった。 19世紀に始まった工業化でもフランスはドイツに遅れをとった。フランスは、イギリスやドイツのような急テンポの産業革命を経験しなかったが、これは担い手となるべきプロテスタントを欠いたことがその一因であった(たとえばフランス人新教徒の技術者デニ・パパンは亡命先のドイツで蒸気ピストンを考案した)。
一方、統一後のドイツの経済発展はめざましかった。人口の都市集中とあいまって、ドイツの工業化はフランスよりも急激な勢いで進んだ。1875年ドイツでは、人口の6割は農村居住者であったが、早くもその8年後には都市生活者が農村を上回った。
だが農業大国のフランスでは、都市人口が農村人口を超えたのは、ようやく1931年になってからのことであった。第二次世界大戦後、西ドイツは「社会市場経済」を実施して奇跡の復興を成し遂げる。一方フランスは、国家主導による経済近代化や国有化を実施したが、国際競争力では自由競争を原理とするドイツが優位に立つことになった。フランスは、たしかに宇宙、航空、原子力、海洋開発など、先端分野では優れた技術と製品を誇るが、輸出市場の規模は限られている。
これに対して、ドイツが得意とする自動車、機械、化学、電機といったものづくりの伝統分野には、より大きな市場のあることが強みとなっている。 一方ドイツとフランスとでは、労使関係や、企業トップにもいちじるしい違いがみられる。ドイツには周知の「共同決定」、つまり労働者の経営参加制度がある。この制度のおかげで、ドイツはフランスに比べると労働争議が圧倒的に少ない。ドイツではストの前に討議を重ねる、フランスでは交渉とストとが同時に始まる、とよくいわれる。またドイツでは大企業経営者の4分の3は、その企業生え抜きの人物によって占められるが、フランスではその割合は4分の1に過ぎない。しかも残りのうち半数は、国立行政学院や理工科学校などのエリート校出身の官僚上がりで、これがしばしば企業内で摩擦を生む結果となっている。
もっとも最近では、経済のグローバル化の中で、ドイツ・モデルは変革を迫られている。国際競争力や労働生産性の点で、ドイツは必ずしも優位に立っていない、という批判がフランスで出ている。なおフランス農業は、EU内でドイツとの摩擦の要因となつているが、これについては後ほどふれる。
だが自然条件の厳しいドイツでは農業だけに依存するわけにはいかなかった。彼らは中世以来商業によって生きる術を身につけ、バルト海貿易を通じて繁栄したハンザ都市をはじめ、多くの都市が交易によって富を集めた。 一方フランスでは、当時商業は貴族の間では「恥ずべき行為」として排斥され、これに従事したものは貴族の特権を剥奪されていた。
宗教改革の時代に、ドイツでプロテスタントが優勢となり、フランスがカトリシズムを貫き通したことも、その後の両国経済の発展に少なからざる影響を残した。
フランスでは1695年、ルイ14世がナントの勅令を撤回して新教を禁止したが、このため20万の新教徒(ユグノー)がプロイセンやオランダに亡命した。これによって国家統一の基盤は強化されたものの、経済発展の活力が奪われたという点では実に大きなマイナスであった。
プロテスタントには、勤勉で技能を身につけ企業家精神に富む人材が多数いたのに対し、金銭を稼いで富を築くことを嫌うカトリシズムは、本質的には近代の資本主義精神にはなじまなかった。 19世紀に始まった工業化でもフランスはドイツに遅れをとった。フランスは、イギリスやドイツのような急テンポの産業革命を経験しなかったが、これは担い手となるべきプロテスタントを欠いたことがその一因であった(たとえばフランス人新教徒の技術者デニ・パパンは亡命先のドイツで蒸気ピストンを考案した)。
一方、統一後のドイツの経済発展はめざましかった。人口の都市集中とあいまって、ドイツの工業化はフランスよりも急激な勢いで進んだ。1875年ドイツでは、人口の6割は農村居住者であったが、早くもその8年後には都市生活者が農村を上回った。
だが農業大国のフランスでは、都市人口が農村人口を超えたのは、ようやく1931年になってからのことであった。第二次世界大戦後、西ドイツは「社会市場経済」を実施して奇跡の復興を成し遂げる。一方フランスは、国家主導による経済近代化や国有化を実施したが、国際競争力では自由競争を原理とするドイツが優位に立つことになった。フランスは、たしかに宇宙、航空、原子力、海洋開発など、先端分野では優れた技術と製品を誇るが、輸出市場の規模は限られている。
これに対して、ドイツが得意とする自動車、機械、化学、電機といったものづくりの伝統分野には、より大きな市場のあることが強みとなっている。 一方ドイツとフランスとでは、労使関係や、企業トップにもいちじるしい違いがみられる。ドイツには周知の「共同決定」、つまり労働者の経営参加制度がある。この制度のおかげで、ドイツはフランスに比べると労働争議が圧倒的に少ない。ドイツではストの前に討議を重ねる、フランスでは交渉とストとが同時に始まる、とよくいわれる。またドイツでは大企業経営者の4分の3は、その企業生え抜きの人物によって占められるが、フランスではその割合は4分の1に過ぎない。しかも残りのうち半数は、国立行政学院や理工科学校などのエリート校出身の官僚上がりで、これがしばしば企業内で摩擦を生む結果となっている。
もっとも最近では、経済のグローバル化の中で、ドイツ・モデルは変革を迫られている。国際競争力や労働生産性の点で、ドイツは必ずしも優位に立っていない、という批判がフランスで出ている。なおフランス農業は、EU内でドイツとの摩擦の要因となつているが、これについては後ほどふれる。
文明と文化
文化についても、両国は、文学、哲学、音楽、絵画など、さまざまなジャンルで、それぞれ際だった個性を示し、両国民の物の考え方や感性に根本的な違いがみられることは周知の通りである。
しかしここで注目したいのは、そうした個々の問題ではなくて、ドイツ人とフランス人が、文化形成の歴史をまったく異にし、また文化そのものについてあい異なる概念をもつているという基本的な問題である。
これについては、名著『フランス文化論』(1930)で知られるドイツの文学批評家、エルンスト・ローベルト・クルティウス(1886-1956)の所論がある。彼は独仏文化の十字路、当時はドイツ領であったアルザスに生まれた。彼の著書は、今日なおフランスでも独仏関係を論じるさいに引用される。第一に、文化形成の歴史の違いについて、クルティウスは明快な指摘を行なつている。彼によれば、「ドイツの歴史はローマに対する反抗に始まり、フランスの歴史はローマに対する服従に始まる」。 ゲルマニア(今日のドイツ)では、紀元9年ゲルマン人のヘルマン(ラテン名アルミニウス)は、兵を率いてトイトブルクの森(北西ドイツ・オスナブリュツクの近郊)でローマ軍団を急襲してこれを壊滅させた。当時ローマ人は、征服したライン左岸以西から、さらに右岸のゲルマニアに勢力を拡大しつつあった。ヘルマンは支配者のローマ人に対して蜂起し、ゲルマニアをローマ人から解放する口火を切ったのである。ローマ人はこの敗北をきっかけに、ライン・ドナウの線まで後退せざるをえなかった。クルティウスのいう「ローマに対する反抗」の始まりであった。 一方ガリア(今日のフランス)では、これとまったく正反対の運命が待ちかまえていた。カエサルのガリア征服の末期、ガリア人のウェルキングトリクスが挙兵して反抗するが、紀元前52年にアレシアで包囲されて降伏する。この敗北でガリアのローマ化が始まり、ガリアは征服者のローマ人から文化を継承することになった。
こうしてガロ=ロマン的なフランス文化の基盤が形成された。クルティウスのいう「ローマに対する服従に始まる」とはこのことを指している。付言すれば、ドイツはその後さらに大きな「ローマに対する反抗」を行う。ルターの宗教改革によるプロテスタントの誕生である。トーマス・マンは、その著書でドストエフスキーの言葉を引用しながらこうのべている。「ドイツ人は歴史世界に登場した最初の瞬間から、その運命においても、その諸原則においても、西欧世界、つまり古代ローマのすべての後継者とは、一度たりとも、一体になろうとはしなかった。 ドイツはこの世界に対し、二千年このかたプロテストしてきたのである」。 第二に、文化の考え方について両者の間にみられる根本的な違いである。フランスでは18世紀後半になって「文化」とは別に「文明」という新しい概念が登場した。この文明<civilisation>という言葉は、古代ローマの市民精神<civitas>に由来し、『ヨーロッパ文明史』を著したギゾーによって概念の体系化が行われた。
フランス人は、文明とは自由の発展の成果であり、人類に普遍的な内容をもつているとして、これを文化よりも高く評価し、フランスこそ文明の先駆者であるとの自負をもつにいたった。 これに対してドイツ人は、文化を文明より上に置いた。ドイツ人にとって「文明」とは物質的で機械化された生活を意味し、精神の世界や芸術の世界、つまり「文化」と対立するばかりでなく、それを脅かす敵でもあった。トーマス・マンが第一次大戦中、大戦をフランスの文明に対するドイツの文化の戦いである、と主張したことはすでにふれたが、その背景にはこうした文化概念の違いが存在していたのである。
しかしここで注目したいのは、そうした個々の問題ではなくて、ドイツ人とフランス人が、文化形成の歴史をまったく異にし、また文化そのものについてあい異なる概念をもつているという基本的な問題である。
これについては、名著『フランス文化論』(1930)で知られるドイツの文学批評家、エルンスト・ローベルト・クルティウス(1886-1956)の所論がある。彼は独仏文化の十字路、当時はドイツ領であったアルザスに生まれた。彼の著書は、今日なおフランスでも独仏関係を論じるさいに引用される。第一に、文化形成の歴史の違いについて、クルティウスは明快な指摘を行なつている。彼によれば、「ドイツの歴史はローマに対する反抗に始まり、フランスの歴史はローマに対する服従に始まる」。 ゲルマニア(今日のドイツ)では、紀元9年ゲルマン人のヘルマン(ラテン名アルミニウス)は、兵を率いてトイトブルクの森(北西ドイツ・オスナブリュツクの近郊)でローマ軍団を急襲してこれを壊滅させた。当時ローマ人は、征服したライン左岸以西から、さらに右岸のゲルマニアに勢力を拡大しつつあった。ヘルマンは支配者のローマ人に対して蜂起し、ゲルマニアをローマ人から解放する口火を切ったのである。ローマ人はこの敗北をきっかけに、ライン・ドナウの線まで後退せざるをえなかった。クルティウスのいう「ローマに対する反抗」の始まりであった。 一方ガリア(今日のフランス)では、これとまったく正反対の運命が待ちかまえていた。カエサルのガリア征服の末期、ガリア人のウェルキングトリクスが挙兵して反抗するが、紀元前52年にアレシアで包囲されて降伏する。この敗北でガリアのローマ化が始まり、ガリアは征服者のローマ人から文化を継承することになった。
こうしてガロ=ロマン的なフランス文化の基盤が形成された。クルティウスのいう「ローマに対する服従に始まる」とはこのことを指している。付言すれば、ドイツはその後さらに大きな「ローマに対する反抗」を行う。ルターの宗教改革によるプロテスタントの誕生である。トーマス・マンは、その著書でドストエフスキーの言葉を引用しながらこうのべている。「ドイツ人は歴史世界に登場した最初の瞬間から、その運命においても、その諸原則においても、西欧世界、つまり古代ローマのすべての後継者とは、一度たりとも、一体になろうとはしなかった。 ドイツはこの世界に対し、二千年このかたプロテストしてきたのである」。 第二に、文化の考え方について両者の間にみられる根本的な違いである。フランスでは18世紀後半になって「文化」とは別に「文明」という新しい概念が登場した。この文明<civilisation>という言葉は、古代ローマの市民精神<civitas>に由来し、『ヨーロッパ文明史』を著したギゾーによって概念の体系化が行われた。
フランス人は、文明とは自由の発展の成果であり、人類に普遍的な内容をもつているとして、これを文化よりも高く評価し、フランスこそ文明の先駆者であるとの自負をもつにいたった。 これに対してドイツ人は、文化を文明より上に置いた。ドイツ人にとって「文明」とは物質的で機械化された生活を意味し、精神の世界や芸術の世界、つまり「文化」と対立するばかりでなく、それを脅かす敵でもあった。トーマス・マンが第一次大戦中、大戦をフランスの文明に対するドイツの文化の戦いである、と主張したことはすでにふれたが、その背景にはこうした文化概念の違いが存在していたのである。
人種的多様性
両国社会の違いは、きわめて多岐にわたるが、ここでは最も重要と思われる2点にしぼることにしよう。
第一は人種的な多様性である。私が40年前にはじめてドイツからパリヘ旅して驚いたことはまさにこれであった。フランス国民が人種的混血によって形成されたことはすでにのべた通りであるが、19世紀末いらいの移民の増加は、この国を人種的にさらに多様化することになった。工業の急激な発展、出生率の低下、労働力の不足など、主として経済的理由からフランスは移民を歓迎した。今世紀のはじめ100万に過ぎなかつた外国人の数は今日では400万(総人口約5860万)を超えている。出身地もさまざまで、南欧諸国のほか、アルジェリアをはじめとする北アフリカのマグレブ諸国、ニューカレドニア、タヒチ、仏領ギアナなど遠く海外植民地におよぶ。 一方ドイツでも、ことに第二次世界大戦後、外国人の数はいちじるしくふえ、トルコをはじめ南欧、旧東欧からの外国人労働者や難民など700万(総人口約8200万)を数えるが、フランスと違ってもともと人種的には均質性を保ってきたので、依然としてゲルマン系が主体をなしている。 もっとも最近両国では、外国人の国籍取得に関して、相反する傾向が顕著となつてきた。フランスではこれまで、外国人がフランス国籍を取得しやすい出生地主義がとられてきた。しかし失業の増大から、右翼の国民戦線の外国人排斥運動が拡大する中で、国籍取得条件が制限される方向にある。
一方ドイツでは、1998年発足した社会民主党(SPD)と「90年連合/緑の党」との連立政権の下で、国籍取得にきびしい従来の血統主義から出生地主義へと転換がはかられつつある。 第二は宗教に関してである。フランスが圧倒的にカトリックの国であるのに対し、ドイツでは新旧両教が併存する。今日、国民の40.8%がプロテスタント、34.8%がカトリックであるが、フランス人にはドイツは、北欧諸国と同様プロテスタント的な性格の強い社会として映っている。社会における教会のプレゼンスは、ドイツはフランスに比べて非常に大きい。
かつてフランスは自らを「ローマ教会の長女」と称し、宗教改革のさいもプロテスタントを追放してカトリシズムを貫いた。しかし革命から共和制の時代を経て、カトリック教会の勢力は後退し、1905年にはついに国家と教会は分離され、フランスは「脱宗教の」国となった。 だがこれと対照的に、ドイツでは教会と国家・社会との間には、依然として不可分の関係が存在する。戦後この国の政治を指導してきた二大政党の一つは、「キリスト教民主/社会同盟」(CDU/CSU)である。公立学枚では宗教教育が行われ、所得税のうち最高10%(州により異なる)が教会税として徴収され、教会の財政にあてられている。日曜日には公共放送を通じて聖職者による講話が流される。いずれもフランスでは考えられないことである。80年代はじめの西ドイツの反核運動の中心となったのは、教会と緑の党であった。ベルリンの壁を崩壊させた東ドイツの自由化運動は、ライプツィヒの教会から始まった。 こうした違いには、やはり歴史的な背景がある。第一に、強力な中央集権国家として発展してきたフランスでは、教会あるいは宗教に対する国家の優位が早くから確立された。第二に、ドイツでは、宗教改革によって新旧両教に分かれたキリスト教が、かえって新たな生命を獲得した。第三に、18世紀にフランスでは「理性」こそ人類進歩の力であるとする啓蒙主義者によってカトリック教会は攻撃され、大革命で国家と教会との緊張関係はさらに強まった。
これに対してドイツの啓蒙主義は、「信仰」と「理性」の結合を貫いた。そしてドイツ統一後も、プロイセンはじめ各邦において新旧両教とも国教的地位を保ったのである。 ちなみに、社会に対する宗教の影響力の違いを示す例として、興味深い指摘がある。何か失敗をして「それは私の落ち度ではない」と言い訳をする時、フランスでは「ス・ネ・パ・マ・フォート」とフォート(英語のミステイク)という日常語を使う。
だがドイツでは「エス・イスト・ニヒト・マイネ・シュルト」という。シュルト(罪)という宗教的表現が依然として日常的に生きているのである。
第一は人種的な多様性である。私が40年前にはじめてドイツからパリヘ旅して驚いたことはまさにこれであった。フランス国民が人種的混血によって形成されたことはすでにのべた通りであるが、19世紀末いらいの移民の増加は、この国を人種的にさらに多様化することになった。工業の急激な発展、出生率の低下、労働力の不足など、主として経済的理由からフランスは移民を歓迎した。今世紀のはじめ100万に過ぎなかつた外国人の数は今日では400万(総人口約5860万)を超えている。出身地もさまざまで、南欧諸国のほか、アルジェリアをはじめとする北アフリカのマグレブ諸国、ニューカレドニア、タヒチ、仏領ギアナなど遠く海外植民地におよぶ。 一方ドイツでも、ことに第二次世界大戦後、外国人の数はいちじるしくふえ、トルコをはじめ南欧、旧東欧からの外国人労働者や難民など700万(総人口約8200万)を数えるが、フランスと違ってもともと人種的には均質性を保ってきたので、依然としてゲルマン系が主体をなしている。 もっとも最近両国では、外国人の国籍取得に関して、相反する傾向が顕著となつてきた。フランスではこれまで、外国人がフランス国籍を取得しやすい出生地主義がとられてきた。しかし失業の増大から、右翼の国民戦線の外国人排斥運動が拡大する中で、国籍取得条件が制限される方向にある。
一方ドイツでは、1998年発足した社会民主党(SPD)と「90年連合/緑の党」との連立政権の下で、国籍取得にきびしい従来の血統主義から出生地主義へと転換がはかられつつある。 第二は宗教に関してである。フランスが圧倒的にカトリックの国であるのに対し、ドイツでは新旧両教が併存する。今日、国民の40.8%がプロテスタント、34.8%がカトリックであるが、フランス人にはドイツは、北欧諸国と同様プロテスタント的な性格の強い社会として映っている。社会における教会のプレゼンスは、ドイツはフランスに比べて非常に大きい。
かつてフランスは自らを「ローマ教会の長女」と称し、宗教改革のさいもプロテスタントを追放してカトリシズムを貫いた。しかし革命から共和制の時代を経て、カトリック教会の勢力は後退し、1905年にはついに国家と教会は分離され、フランスは「脱宗教の」国となった。 だがこれと対照的に、ドイツでは教会と国家・社会との間には、依然として不可分の関係が存在する。戦後この国の政治を指導してきた二大政党の一つは、「キリスト教民主/社会同盟」(CDU/CSU)である。公立学枚では宗教教育が行われ、所得税のうち最高10%(州により異なる)が教会税として徴収され、教会の財政にあてられている。日曜日には公共放送を通じて聖職者による講話が流される。いずれもフランスでは考えられないことである。80年代はじめの西ドイツの反核運動の中心となったのは、教会と緑の党であった。ベルリンの壁を崩壊させた東ドイツの自由化運動は、ライプツィヒの教会から始まった。 こうした違いには、やはり歴史的な背景がある。第一に、強力な中央集権国家として発展してきたフランスでは、教会あるいは宗教に対する国家の優位が早くから確立された。第二に、ドイツでは、宗教改革によって新旧両教に分かれたキリスト教が、かえって新たな生命を獲得した。第三に、18世紀にフランスでは「理性」こそ人類進歩の力であるとする啓蒙主義者によってカトリック教会は攻撃され、大革命で国家と教会との緊張関係はさらに強まった。
これに対してドイツの啓蒙主義は、「信仰」と「理性」の結合を貫いた。そしてドイツ統一後も、プロイセンはじめ各邦において新旧両教とも国教的地位を保ったのである。 ちなみに、社会に対する宗教の影響力の違いを示す例として、興味深い指摘がある。何か失敗をして「それは私の落ち度ではない」と言い訳をする時、フランスでは「ス・ネ・パ・マ・フォート」とフォート(英語のミステイク)という日常語を使う。
だがドイツでは「エス・イスト・ニヒト・マイネ・シュルト」という。シュルト(罪)という宗教的表現が依然として日常的に生きているのである。