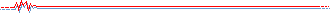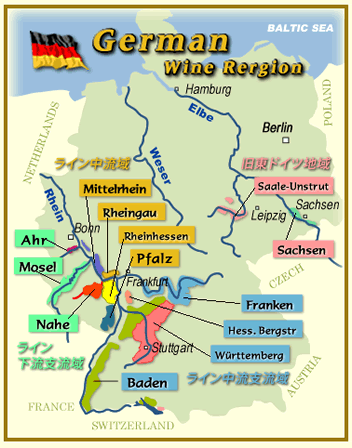ドイツワインの歴 史ー3
神聖ローマ帝国
フランク王国から誕生した東フランク(ドイツ)と西フランク(フランス)は、その後まったく対照的な発展を遂げていった。
東フランク(ドイツ)を引き継いだザクセン朝のオットー1世(936~73)は、国内の反乱を治めると共に、東方のアジア系、北方のスラヴ系異教徒を押さえ、征服地に司教座を設けキリスト教布教にも努めた。またイタリア遠征を行い、イタリアの支配権も確立した。
962年、ローマで教皇から帝冠を受け、自ら「神聖ローマ皇帝」と称した。これにより彼は神聖ローマ帝国(ドイツ帝国)の創始者となった。 しかし「神聖ローマ皇帝」を称する歴代のドイツ国王は、キリスト教を基盤に、古代ローマ帝国を夢みてイタリア支配に多大の精力を注ぎ、それがドイツの国家としての発展をいちじるしく阻害することになる。
オットー3世(在位983~1002年)のごときは、ゲルマン、ローマ、スラヴの3民族を包含して、首都をローマとする世界帝国再興の夢に熱中した。彼は国事をよそにしばしばイタリアに赴いた。ドイツ皇帝のこのイタリア政策は、ザクセン朝の後、さらにザリエル朝、シュタウフェン朝へと引き継がれていく。 一方、西フランク(フランス)の方は、ローマ教皇から帝冠を受けることもなかったし、空疎な古代ローマ帝国の観念にとらわれることもなかった。フランス王朝は、ひたすら王権の強化・拡大に先進し、ローマ帝国を支えた統治組織である中央集権制度の確立を急いだ。
東フランク(ドイツ)を引き継いだザクセン朝のオットー1世(936~73)は、国内の反乱を治めると共に、東方のアジア系、北方のスラヴ系異教徒を押さえ、征服地に司教座を設けキリスト教布教にも努めた。またイタリア遠征を行い、イタリアの支配権も確立した。
962年、ローマで教皇から帝冠を受け、自ら「神聖ローマ皇帝」と称した。これにより彼は神聖ローマ帝国(ドイツ帝国)の創始者となった。 しかし「神聖ローマ皇帝」を称する歴代のドイツ国王は、キリスト教を基盤に、古代ローマ帝国を夢みてイタリア支配に多大の精力を注ぎ、それがドイツの国家としての発展をいちじるしく阻害することになる。
オットー3世(在位983~1002年)のごときは、ゲルマン、ローマ、スラヴの3民族を包含して、首都をローマとする世界帝国再興の夢に熱中した。彼は国事をよそにしばしばイタリアに赴いた。ドイツ皇帝のこのイタリア政策は、ザクセン朝の後、さらにザリエル朝、シュタウフェン朝へと引き継がれていく。 一方、西フランク(フランス)の方は、ローマ教皇から帝冠を受けることもなかったし、空疎な古代ローマ帝国の観念にとらわれることもなかった。フランス王朝は、ひたすら王権の強化・拡大に先進し、ローマ帝国を支えた統治組織である中央集権制度の確立を急いだ。

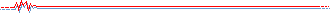
ヴォルムスの協約 (1122年)
ヴォルムスにおいて、ハインリヒ5世が教皇特使とが結んだ妥協の解決で、その内容は、霊的司牧者としての司教の叙任と、司教領の支配者としての司教の持つ世俗的支配権の授与を原理的に区別し、前者は教皇、後者は皇帝のみが行なうものとしている。
言換えれば、皇帝は、司教を任命する権利(叙任権)は放棄し教皇の特権とするが、司教の持つ大きな所領の世俗的支配権は、皇帝が司教に授与するもので、教皇は関与出来ない。つまり、皇帝と当該司教は封建的主従関係を取り結ぶ、と言うことである。
神聖ローマ帝国の権力構造
オットー1世が、カール大帝と同じように、国内統治に教会を利用したが、その異なるところは、世俗の大貴族(地方に定着して世襲によって力を貯えた)に対する対抗勢力として、意図的かつ積極的に教会を利用したことにある。
いち早く中央集権化を成し遂げたローマ・カトリック教会の組織の要は、司教座や修道院である。都市の第一人者である「司教」は、信仰生活における長と言うより、都市住民の世俗的な日々の生活を様々な形で左右しうる行政の長としての役割を担っていた。修道院と共に、この司教は、土地の寄進や各種特権を与えられ手厚く保護されていたから、財政的にも豊かになり、その地方の大権力者になって行った。
聖職者は世俗諸侯と違って結婚しない。従って世襲はない。オットー1世以降、歴代の王は、この聖職者の任命権を握ることによって、教会組織を国の統治機構として利用して行ったのである。 この世俗権力者による聖職者の叙任は、聖職売買や聖職者の堕落という事態を招くことが少なくなかった。
ローマ教皇の権力が伸張する中で、この司教を任命する権利(叙任権)をめぐる争いが頻発するようになって行った。「叙任権闘争」と呼ばれる皇帝と教皇との争いである。 同時に、諸侯の間に皇帝派(ギペッリーニ)と教皇派(グェルフィ)に分かれての対立抗争も生まれた。 この「叙任権闘争」は1122年「ヴォルムスの協約」で妥協の解決を見るが、 神聖ローマ帝国の帝権は、自立的領域支配圏を持つ世俗諸侯と司教座に君臨する聖界諸侯の支持を常に必要とする中央集権とは程遠いものであった。
勿論、フリードリッヒ2世のような例外時期もあるが、持続する強固な政権を持ち得なかったのが神聖ローマ帝国の特徴で、実質的な権力を持つ聖俗の諸侯が並び立ち、19世紀まで統一国家を築き得なかったドイツの要因でもある。
聖職者は世俗諸侯と違って結婚しない。従って世襲はない。オットー1世以降、歴代の王は、この聖職者の任命権を握ることによって、教会組織を国の統治機構として利用して行ったのである。 この世俗権力者による聖職者の叙任は、聖職売買や聖職者の堕落という事態を招くことが少なくなかった。
ローマ教皇の権力が伸張する中で、この司教を任命する権利(叙任権)をめぐる争いが頻発するようになって行った。「叙任権闘争」と呼ばれる皇帝と教皇との争いである。 同時に、諸侯の間に皇帝派(ギペッリーニ)と教皇派(グェルフィ)に分かれての対立抗争も生まれた。 この「叙任権闘争」は1122年「ヴォルムスの協約」で妥協の解決を見るが、 神聖ローマ帝国の帝権は、自立的領域支配圏を持つ世俗諸侯と司教座に君臨する聖界諸侯の支持を常に必要とする中央集権とは程遠いものであった。
勿論、フリードリッヒ2世のような例外時期もあるが、持続する強固な政権を持ち得なかったのが神聖ローマ帝国の特徴で、実質的な権力を持つ聖俗の諸侯が並び立ち、19世紀まで統一国家を築き得なかったドイツの要因でもある。